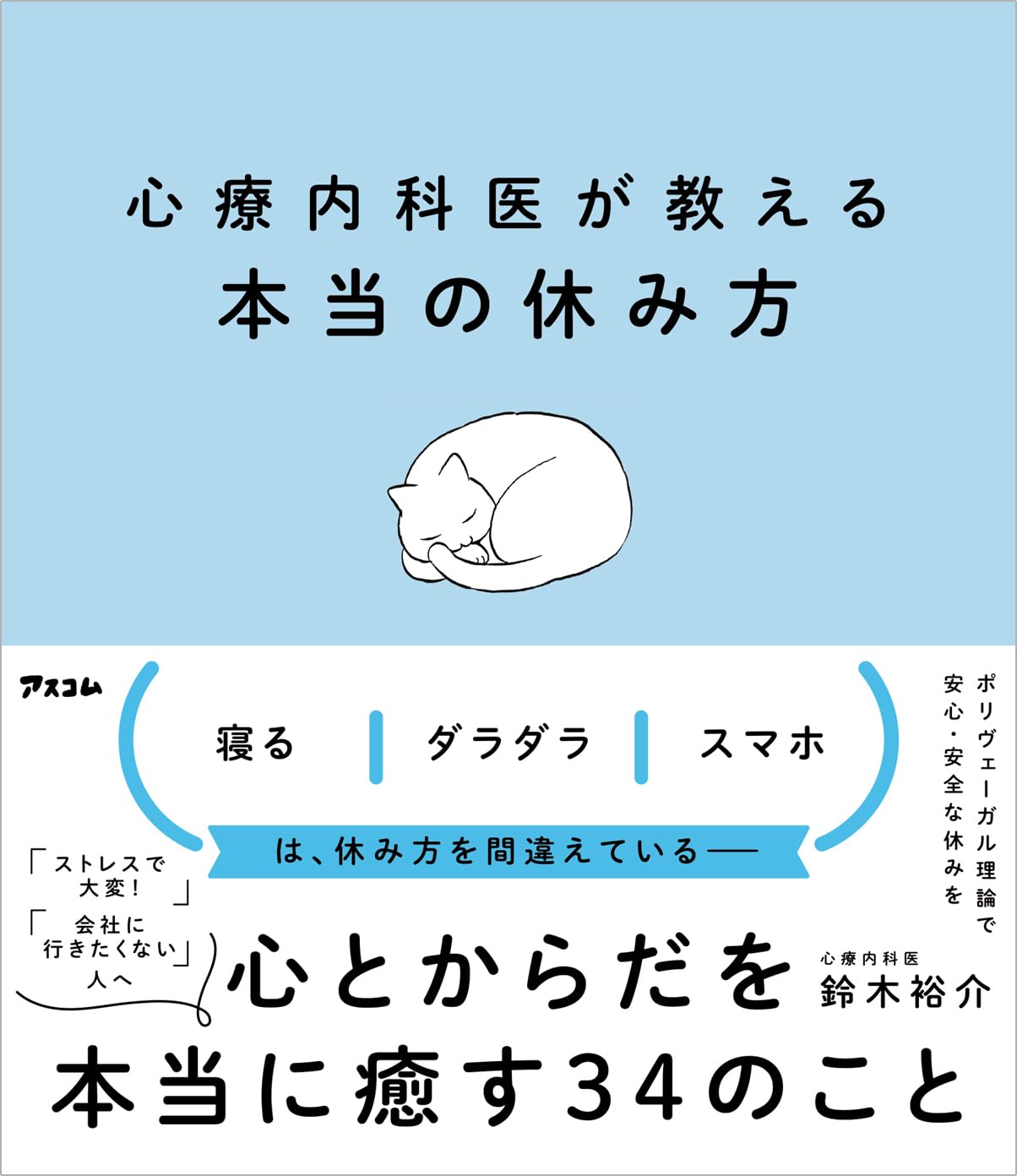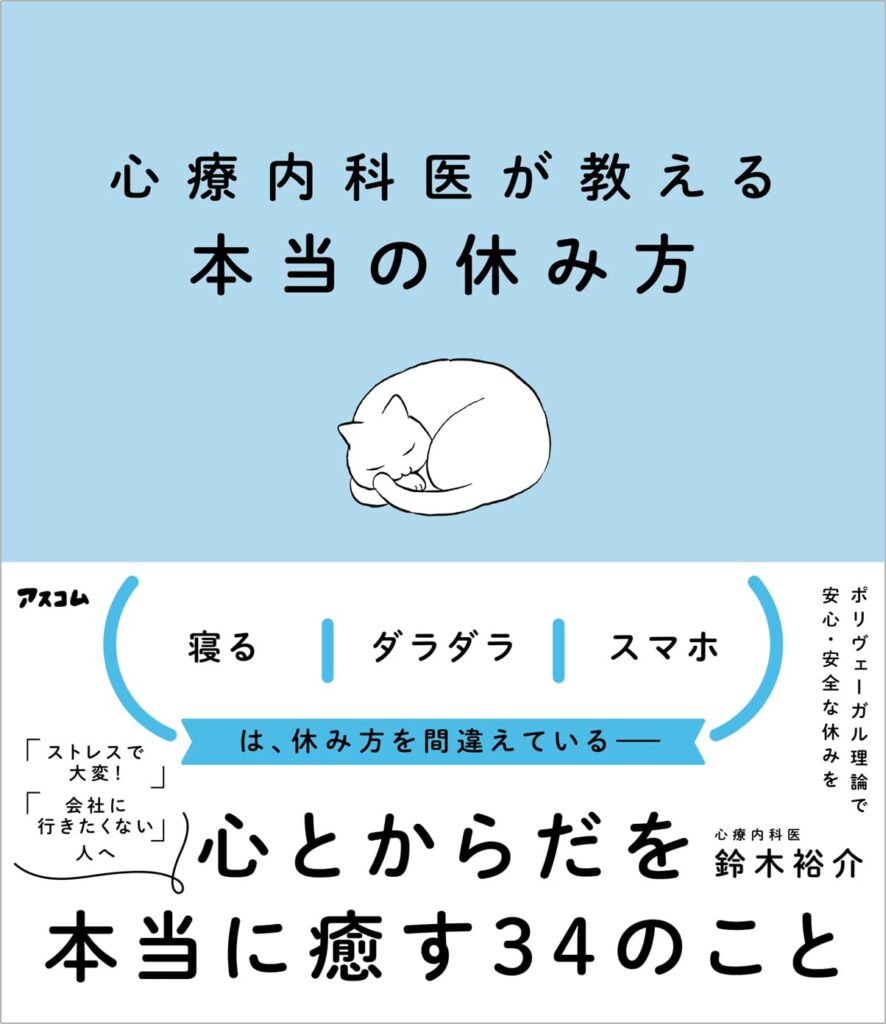
上手く復職場になじめるのか…?
1年半の育休を終え、いよいよ来週から職場復帰をする私。。
実は前回の復職では、上司と折り合いが悪く、上手く職場になじめませんでした…。
そんな苦い経験が影響して、現在、メンタルはグラグラ 笑
果たして今回は上手く職場になじめるのか…?
仕事と育児を両立してこなしていくことはできるのか…?
そんなときに、手にしたのがこの一冊。
「心療内科医が教える 本当の休み方」 鈴木裕介 著 です。
この本には、「えっ!そうなの!?」「なるほど~」「ホントその通り!」と
色々な発見と、気づきがあったのでぜひ共有したいと思います。
”きちんと休む”は難しい
現代は約8割りの人が、「休んでいるのに疲れが取れない」「休みたくても休めない」という慢性的な疲労を抱えている状態だといいます。
”きちんと休む”には高度が技術が必要とのこと。
さらに、離婚や死別だけでなく、結婚や昇進などのライフイベントや
もっというと、「SNSで好きじゃない口調の投稿を見た」とか「あの人のちょっとした態度」など日常のちょっとしたことまでもが、ストレスになりうるため
もはや、ストレスを回避するのは不可能!
というか、適度なストレスはむしろ健康に生きるのには必要不可欠。
適度なストレス状態を保つことが重要となります。
大事なのは、これらの自分にとってストレスだと感じることを見て見ぬふりをするのではなく、
ストレスがあるなーと自覚すること。
(ストレスを感じたらメモすることもいいそうです、私もやろうと思います!)
①ストレスを自覚して→ ②休む環境を整えて → ③自分にとって適切な休養活動をすること
これが休むために必要なプロセスです。
「他人の期待に応えたい」を手放す
休むことを難しくしている大きな原因が「過剰適応」。
これは、周りに配慮しすぎて常に気を張っている状態のことです。
自分の居場所を作るため、安心を得るために真面目な人ほど、この「過剰適応」に陥りやすいのですが、これをしている限り、自分の心や体のニーズにこたえて、しっかり休むことはできません。
なので、しっかり休息するためには、この「他人の期待に応えたい」気持ちを手放す必要があるのです。
でも、育休中の私がまさに、そうでしたが、嫌な上司から離れても、「働けてない自分」を自分自身が必要以上に責めて、自分を許せていないと、これまた、きちんとした休息にはつながりません。
あぁ、反省。。
自分自身も敵になりうるなんて、、休むって難しい。。
新しい副交感神経!?
ここが、本書で私が一番びっくりしたとこ!
これまでは、「自律神経の乱れが現代人のストレスの原因。
交感神経に入ったままの状態から、副交感神経が優位の状態に戻すことが大事」だと言われてきました。
だから、ストレスがあると湯船にゆっかり浸かれだとか、リラックスして音楽を聴けだとか言われますよね、よく。
でも、実は交感神経と副交感神経だけでは説明できないケースが増えてきているのです。
例えば、会社で上司に必要に責められて、どんどん無気力・無表情になっているAさん。
上司に叱責されるほど、頭が真っ白になり反論もできず、次第にできることもできなくなり、ますますパフォーマンスが落ちていき、次第に出社できなくなってしまいました。
(まさに、前回復職時の私みたい!)
この状況は明らかに、交感神経が優位になっている状態とは違います。
でも、リラックスモードの副交感神経とも違いますよね。
これが、ポージェス博士という人が発見した、新しい副交感神経「背側迷走神経」が優位になっている状態です。
つまり、副交感神経には、リラックスモードの「腹側迷走神経」と
この凍り付いてパフォーマンスが低下する「氷のモード」を発動する「背側迷走神経」の2つがあることが発見されたのです!
これは強いストレスが続いたときに、自分を守る防衛本能が働いた状態だと言えます。
強いストレスに対して、交感神経は「闘う」「逃げる」などで応戦しますが
この背側迷走神経は「凍りつく」「無感情になる」ことで自分を守ろうとします。
大事なのは、自分がどちらの状態にいるのかを自覚すること!
なぜなら、これらの2つの状態は対応が全く異なるからです。
<交感神経が優位になっている場合>
・ゆっくり呼吸する
・ハーブティーやアロマで落ち着く
・静かな音楽を聴く
・温かい湯船につかる
・部屋を暗くする
<背側迷走神経が優位になっている場合>
・早めの呼吸をする
・運動や体操で体を動かす
・エキサイトするゲームや音楽
・太陽の光を浴びる
⇑のように対応が全く真逆!
今までの、ストレスにはリラックス!という知識だと、逆効果の対応をしてしまうかもしれないのです。
これは目から鱗でした!なるほど~!
思うように動けないのは、あなたのせいじゃない
会社や学校に行かなきゃ!という気持ちはあるのに、いざ動こうとすると上手くできない。
疲れてるわけじゃないのに、なんだかぼんやりして、モチベーションがわかない。。
こんなときは、この背側迷走神経が優位になって「氷のモード」になっているせいかもしれません。
この症状は、思春期に多い「起立性調節障害」とも合併していることも多いそうで。
これは、たとえ本人が「学校に行きたい」という気持ちを持っていても起こります。
その気持ちとは裏腹に、身体が危険を感知してブレーキをかけているのかもしれない。
でも、その状態の子は、親から見ると…
「シャキッとしてない」「やる気がない」「さぼっている」ように見えるのです。
そうして、叱責するとそれがストレスになり、さらに背側迷走神経が強く出る悪循環…。
この話を、不登校経験のある子たちにすると、「まさにこれだった!」という子が多数いるそうです。
危険な場所に行きたくない!という身体からの切実な訴えなんですね。
やっぱり子どもが「学校に行きたくない」と言ったら、理由はなんであれ、休ませてあげることが大事なんだなと思わされます。
不登校の原因なんて、本人も分からない場合がほとんどだって言いますしね。
じゃあ、どうすればいいのか?
自分の状況は分かった。じゃあ、具体的にどうやってストレスに対応して、休めばいいのか?
それが何より知りたいですよね。
そこで、大事になってくるのがリラックスモードをつかさどる「腹側迷走神経」です。
「腹側迷走神経」が優位になる状態は、「安心・安全」が感じられる状態のこと。
つまり、心理的安全性が確保された環境ってことですね。
否定せずに話を聞いてくれる、家族や友人とリラックスして会話する時間がストレス緩和に大事なんですねぇ。
でも、「友達なんていないよ…」「安心して何でも話せる人なんて大人になると作るのは難しい…」という人!(私)
安心してください!
つながる相手は、人じゃなくてもいいんです!
ペットとか、ライナスみたいに毛布やぬいぐるみでもいい。
亡くなった人が見ていてくれる、と思ったり、絵画の中の人の暮らしに思いをはせたり、
自然の風を感じたり、歴史的建造物を見て、自分へと続く歴史を感じる…。
つまり、自分が大きなネットワークの一員であると感じられればそれでOK。
こういうつながりを感じることが、「生きる力」や「癒し」の元となるのです。
あとは、
<クラウディング:いま、ここにいる感覚を取り戻す方法>
・椅子に座っている座面に意識を集中する
・木や金属を握りしめて手応えを感じる
・毛皮やぬいぐるみなど手触りがいいものを撫でる
・バランスボード
・裸足で砂浜や土、芝生を歩く など
<内受容感覚を感じる練習>
・頭のてっぺんからつま先まで、じっくりの自分の身体の内側に注意を向けてみる
→緊張している部分、違和感を感じる部分にねぎらいの気持ちを向ける
・自分が本当に食べたいものを考える
・水を一口飲んで、水の感覚をどこまで追いかけられるか毎朝チェックする
などが紹介されていました。
つまり、今の自分の身体にきちんと意識を向けるってことですね。
私もさっそく取り入れてみようと思います♪
人と繋がりたくない…けど繋がりたい矛盾を抱える私たち
私が、まさにその通り!
今の私の気持ちを代弁してくれてるわ~と思ったのが、ここ!
現代は、誰でもやってしまうちょっとした失敗や失言が、赤の他人からもSNS等で必要以上に責め立てられる時代。
人間関係はますます繊細で、難易度が高くなっています。
私もそうですが、傷つきたくないので、人とのつながりをどんどん縮小していってしまいがちです。
私の場合は、出産、育児を経て、友人がぐっと減り、どんどん疎遠になっていきました。
人と付き合わないってすっごく楽なんです。
自分を必要以上に傷つけられないし、自分が意図せずに傷つけてしまうこともない。
しばらくは、なんて快適なんだ~と思っていました。。
…が!やっぱり人間って社会性を持った動物なんですね。
私の中にも、ふつふつと人と繋がりたい欲求がわいてきて抑えられないのです。
関わる人が多ければ多いほど、ストレスが増えることは分かっているのに、
それでも、誰かとつながりを求めることをやめられない!
本書にも、まさにそれが書かれていて、防衛本能の「つながりたくない」と
哺乳類のDNAに刻み込まれてきた「つながりたい」がぶつかり合っていることが
現代人の生きづらさを生み出している、と。
まさに!
私の苦しみを表現してくれてるよ~~
そして、この本が伝えてくれているのは、
別に他人と「つながる」のも、「つながりたい」のも、どちらかが正解なわけではないけど、
人間関係に疲れ、傷つき、「もう誰とも接したくない」「二度と他人は信じられない」と思っても、私たちの神経には一生を通じて変化していく力があるので、
また人間関係の中で、自分の癒しや安心になるつながりを得ることは、全然できるよ、と。
何度、絶望しても、再び希望を見出す可能性は、たくさんあるよ、と教えてくれています。
一回の絶望であきらめなくてもいいんですね。嬉しい。。
困難から回復する力BASICPh
では、最後により具体的な強いストレスからの立ち直りのメカニズム6種類を紹介します。
それが、BASICPh。
人が強いストレスを受け、世界とのつながり方を見失ったときに、再び世界とのつながりのきっかけをつかむ「物差し」となるものです。
つまり、自分の回復パターンを理解して、より増やしておこう!ということ。
順番にご紹介します。
<B:Belief(信念・価値)>
宗教的信念、使命感、自己達成欲求など、信念や価値に頼る
<A:Affect(感情・情動)>
泣く、笑う、自分の感情体験を他人に話す
<S:Social(社会的)>
仕事や役割を引き受けることで、組織の一員となり、支えを得る
<I:Imagination(想像力)>
夢想にふける、クリエイティブな活動をする、想像によって現実に蓋をして気を紛らわす
<C:Cognition(認知)>
情報収集をする、自分と対話する、優先事項を洗い出すなど、問題解決に向けて動く
<Ph:Physiology(身体)>
身体を動かすことでストレスに対処する
どれに当てはまりましたか?
私は、自分が強いストレス(親の死など)に直面したときのことを思い返すと…
完全にC:Cognitionでした。
当時は、苦しくて苦しくて、どうしていいか分からなくて
何か道しるべとなるものが、欲しくて、手あたり次第本を読んでいたことを思い出しました。
それで、「禅」の考え方に救われたんだよなぁー。
物事をありのまま受け入れる、そこに意味はない。今でも自分のベースになっている気がします。
今まさに、復職に向けての不安を、本を読んで解消しようとしているのも、これですね。笑
このように、自分がどのチャンネルによって、より心身の回復が早いか、を理解しておくことがとても大事です。
そして、もちろん1つのチャンネルだけでなく、複合的に影響し合っていたり、組み合わせて使っていることもあります。
もちろん、新しいチャンネルを開拓することも☆
一般的に、隣のチャンネル同士は開拓しやすいと言われています。
なので、私の場合、I:Imagination を取り入れたり
(すでに、漫画や小説が大好きでイヤなこと忘れるために読んだりしてますね)
Ph:Physiology を取り入れたりすることで、よりストレスへの対処法を増やすことができるということ。
ただ、ストレス解消をしましょう~と言われるより
より自分に合ったものを見つけることができて、これはかなり使えそう!
さっそく、取り入れてみようと思います。
私に必要なのは、ここら辺かなー
I:Imagination
・写真を撮る
・演劇を観る
・創作活動をする
・ファッション・メイク
・ユーモアを大事にする、あえてふざける
Ph:Physiology
・掃除・散歩
・料理
・大声を出す
・温泉
・アロマセラピー
あなたもぜひ、自分にあったチャンネルを見つけてみてください。
終わりに
本書の最後で
「あなたを大事にしない人を、あなたが大事にする必要はない」逆もまたしかり
と、書かれていて本当にそうだなーと思いました。
人生ってあっという間で、自分のことを大事にしない人にかまっているヒマなんてありません。
それよりも、自分を好きでいてくれる人、大事に思ってくれる人たちとの時間に
もっともっと思いをはせて、大事にしたい。
この信念で、復職後の仕事に臨んでいきたいと思いました。
いやーいいタイミングで良い本に出合えたなぁ。感謝!
そして、どんなときもユーモアを忘れないこと。
シリアスになればなるほど、人は「氷のモード」に入ってしまいます。
そうすると、より自分の能力や良さが発揮できない。
つらいときこそ、ふざけて笑い飛ばしてやれ!
休めなくて苦しいとき、自分に合った休み方が知りたいとき、みなさんも、ぜひ、読んでみてください。