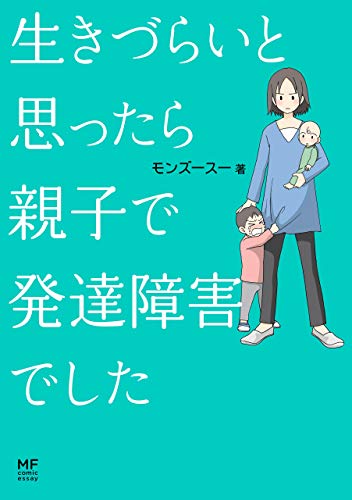
ひらひら恐怖症
うちの息子ちゃんは、小さいころ(今も小さいですが 笑。1,2歳の頃です)
カーテンとか、垂れ幕とか、ひらひらするものを異様に怖がっていた時期がありました。
保育園でもお昼寝の際に引くカーテンが怖くて、パニックになって寝れないことが度々。
さらに忘れられないのが、夜間の緊急外来にかかったとき
(古い青魚を食べさせたため、湿疹が出て慌てて受診しました…)
病院の受付に貼ってある紙が、ひらひらして怖かったようで
どれだけなだめてもパニックが収まらず、とうとう引っ張り取ってしまったことがありました。
そのころ、ちょっと自閉症とか発達障害の疑いがあるかもなーと思い
いろいろ本を読んでいた中の一つ。
「生きづらいと思ったら親子で発達障害でした」モンズースー
こちらを、今回はご紹介します!
子育てって知識がいる
この本は、作者のモンズースーさんが、息子さんのひどい癇癪に悩むなかで、
はじめて自身と息子さんの発達障害に気付き、いろいろと悩みながら工夫して自分たちの生き方を確立していくお話です。
可愛いシンプルな絵で描かれたマンガなのですごく読みやすいです☆
自分がなんか他の人と違う、みんなが問題なくできることが自分にはできない
なぜか分からないけど生きづらい!そんな思いを抱えながら生きてきたモンズースーさん。
それでも、一人暮らしの時は、片付けができないから物を増やさない、家具を置かない、など
自分なりに工夫して暮らしてきました。
ところが、結婚し、母親になり、息子さんの不眠とひどい癇癪に悩まされるようになります。
さらに、旦那さんの単身赴任 & 発覚した2人目の妊娠
そんな中、ネットの情報により自分と息子さんの発達障害の可能性に気付きます。
医学的には発達障害の遺伝は証明されていないそうですが
実感的にはかなり遺伝性あり!
自分の今までの生きづらさの理由は分かったけど、これから息子はどうなるのか
お腹にいる子も同じように発達障害なのか。
どうやって生きていったらいいのか…ワンオペ育児の中でどんどん追い詰められてしまいます。
それでも、自分で心療内科に出向いて、発達障害の診断を正式にもらったり
グレーゾーンと診断された子どもの療育を始めたり、最適な保育園を探したり、少しずつできることを始めていきます。
その姿勢がとても共感できるし、自分で考えて工夫している姿が尊敬できます。
モンズースーさんは、ホント諦めず、自分に合わせて工夫を続けているんです。
それがすごい!
例えば、不安でいっぱいで精神的に行き詰ってしまったら
全部忘れて子どもを連れて、遊べるホテルでストレス発散したり
(こういう息抜きって大事だけど、なかなか踏ん切りがつかないもの)
地方に引っ越して車の運転が必要になった際も、自分の特性をよく理解して
なるべく大通りを通る、遠くても周りに車のいない駐車場に停める、歩けるところには歩いていくなど、手間がかかっても人と一緒にしようとせずに、自分なりの工夫をしているところがすごくいい!
私はつい、ひと手間を惜しんでなるべく近くの駐車場探したり、少しでも時短になる方法をつい選んでしまうけど、別に人より時間や手間がかかったっていいじゃない!
自分なりの方法で、より安全な方が絶対いい!と思えました。
それにしても、子育てって知識がいるっていうのを改めて実感しました。
ひどい癇癪もパニックも、知らない人から見たら、わがままな子、もしくは
しつけができてない親のせい、と見えるかもしれません。
でも、本当は本人も自分の気持ちの伝え方が分からなくて困っているのかも。
もしかして発達障害なのかも?と思える知識がないと
その子に合わせた療育も始められません。
さらに、療育や保育園の内容にも地域によってかなりバラつきがあるようで
地域によっては(という担当の人の問題?)「そんな癇癪なんて誰にもあるわよー」で済まされてしまったり、本当にいろいろのようです。
つまり!地域の行政だけに頼っていては受けるべき教育を受けられないのかもしれないということ!
自分で知識を持って、自分で必要な教育や治療をつかみ取らなくてはいけないのです。
覚えておきたい参考情報
そんな本書の中で、参考になるな!覚えておきたい~と思った
子どもに対するアプローチをご紹介します♪
「生きづらいと思ったら親子で発達障害でした」モンズースー
・言葉にこだわらず伝わることを楽しませる(開けてー/むいてほしいの?)→言葉が増える
・言葉がけ(右足履くよ/手洗うよ)/目の高さに物を持ってきてアイコンタクト
・事前に予定を伝える(写真付き)
・癇癪→抱っこ→気持ちを代弁→解決法の提案
・ダメなことをしていい場所を与える(吐き癖/洗面所、落書き/紙、物を蹴る/ボール)
・食べ歩き→イスを一緒に買う→お盆の分が自分の分→TVやオモチャはなくす
・触っちゃいけないところに「×」を張る
・出来ないことは半分一緒にやってあげる
・始まりと終わりを伝えておく
・苦手は小さな成功体験をたくさんさせる
・言葉より絵、写真、動画で伝える
こう見ると、やはり「可視化」や「見通し」がポイントだなぁと思いますね。
私もつい、自分の都合通りに進めようとしてしまいがちですが、
子どもに、子どもの目線で、分かるように、見通しを共有する ってのが大事☆
自分だってこの先どこに連れていかれるのか、何をするのか分からなければパニックにもなります。
子どもの態度で自分の至らなさを実感する日々です。。
(昨日も自分だけ歯磨き後にジュースを飲んで、指摘された)
まとめ
結局、うちの息子ちゃんのひらひら恐怖症は成長とともになくなりました。
でも一時期はホントひどくて、サーカスを見に行った際には空中ブランコで
巨大な垂れ幕がひらひらして泣き叫び、外に出ざるを得ませんでした。。
あれはなんだったんだろう…今でも物事へのこだわりは強めです。
ちなみに、このシリーズのモンズースーさんの本は全部で3冊あり
「入園編」と「入学準備編」もあり、全部読むと小学校入学までの流れが分かるようになっています。
全部読みやすくて、参考になるので是非どうぞ♪









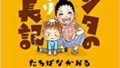
コメント
wow, awesome post.Much thanks again. Will read on…
A big thank you for your blog post.Really looking forward to read more. Awesome.
This is one awesome article. Really Cool.
Thank you ever so for you article post.Thanks Again. Much obliged.